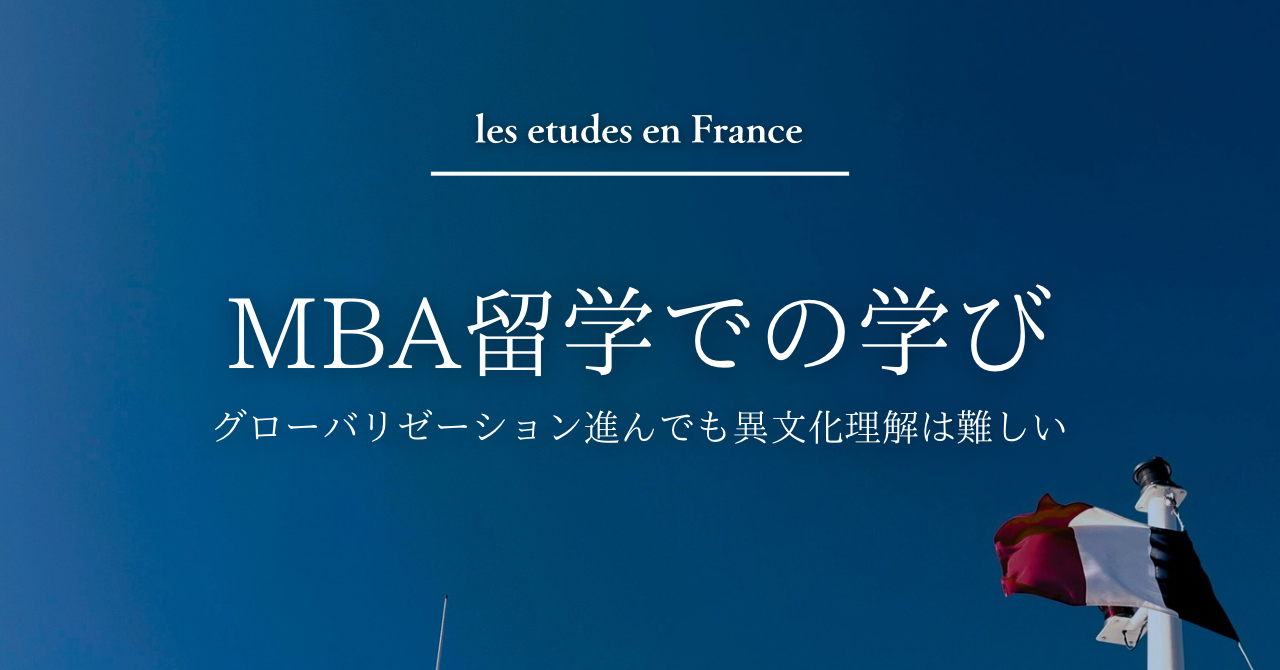Last Updated on 2025年10月11日
MBA留学が始まってから早くも3週間が経ちました。
日本での大学生活はずいぶん前になりますが、授業のスタイルがだいぶ異なることを実感しています。
こちらではほとんどすべての授業にグループワークやディスカッションが組み込まれており、さらに共同で進める宿題やプロジェクトが課されます。
受け身で講義を聞くスタイルに慣れきっていた私にとって、最初の1週間は体力的にも精神的にも大変でしたが、ようやくリズムに慣れてきたところです。
そんな折に「多様性とインクルーシブ考える」という単発の授業がありました。テーマはずばり「文化」。元々は長らくロンドンで弁護士だった先生による授業で、人間の奥深い価値観を掘り下げる試みでした。
自分の文化を語るグループワーク
セミナーで最初に行ったのは、国籍やバックグラウンドの異なる学生たちが集まって「自分の文化」を語り合うグループワークです。互いに「コミュニケーションで驚いたこと」や「社会のしきたり」「無意識の常識」についてざっくばらんに話し合いました。
普段は当たり前すぎて言語化すらしたことのない「自分の文化」を、改めて他者に説明する作業は予想以上に難しく、同時に新鮮な体験でした。
自分にとって自然なことが相手にとっては不可解であったり、逆に相手の「普通」が自分にとっては驚きであったりする。その繰り返しの中で、文化という目に見えない壁の存在を強く意識しました。
日本の「当たり前」は世界の「当たり前」ではない
私は日本で生まれ育ち、これまでの勤務経験も日本人が大半を占める組織に限られていました。そのため日常生活において「文化」を強く意識することはほとんどありませんでした。しかし、このセミナーを通して改めて実感したのは、自分が「普通」だと信じて疑わなかったことが、他者にとっては「異常」や「奇妙」に映る可能性があるという事実です。
たとえばタトゥー。日本では今でも温泉やプールといった公共施設で「入墨お断り」という張り紙をよく見かけます。私にとってもそれは子どもの頃から見慣れた日常風景でした。ところがクラスメイトにその話をすると、「なぜ?」という表情を浮かべられるのです。彼らにとってタトゥーは、ファッションや自己表現の一部。歴史的な「反社会的勢力」との結びつきを知らない人にとっては、むしろ禁止する方が不思議に映るようです。「温泉に入れないんだよ」と説明するとなんでと目を丸くされ、こちらも思わず苦笑いしてしまいました。
また「沈黙」の価値観も大きな違いを感じたテーマでした。日本では「沈黙は金」という言葉があるように、場を乱さずに静かにしていることが美徳とされる場面が少なくありません。会議でも、黙ってうなずくだけで「理解している」「賛同している」と受け止められることがあります。しかし欧米の文化では沈黙はしばしば「意見がない」「準備不足」と見なされるそうです。実際に議論の中で「なぜ黙っているの?意見が欲しい」と指摘される場面もありました。沈黙は尊重なのか、それとも障害なのか。
同じ行為でも文化によって意味がまったく変わることを肌で感じました。
「アメリカ人」というステレオタイプ
さらに印象的だったのは、私たちアジア人のクラスメイトが、無意識のうちに「アメリカ人」をひとくくりにしていたことです。セミナーで文化を語り合う中で、「実は自分にとって“アメリカ文化”は複雑なものだ」という声を聞きました。そこには、何世代にもわたってその土地に根ざしてきた人もいれば、親の代で移民してきた人もいて、意見はばらばら。アメリカ国籍を持っているからといって、背景が同じとは限りません。
私たちは往々にして「アメリカ人だからこうだろう」と安易に決めつけてしまいがちです。ステレオタイプに頼ることで思考が楽になる一方、相手を正しく理解するチャンスを失ってしまう。多様性を学ぶために留学しているはずの私自身が、実はステレオタイプの罠にはまっていたのだと気づかされました。
クラスメイトの「マルチタスク力」に驚く
少し脱線しますが、授業中に見たクラスメイトの行動も、多様性のひとつの現れかもしれません。隣の席の学生が熱心にキーボードを叩いているので「議論のメモでも取っているのかな」と思って覗いてみると、実はクラスメイトとチャットをしていたり、航空券の予約をしていたりするのです。
あら、授業中にそんなことを……!と驚く私の前で教授に突然意見を求められると、彼らはまるで最初から議論に集中していたかのように的確な答えを返します。私の感覚では授業中に別のことをするのは失礼だと捉えがちですが、彼らにとっては効率的な時間の使い方のひとつなのでしょう。私には真似できませんが、その器用さと集中力には感心します。これもまた「学び方の多様性」なのかもしれません。
「聴く」という姿勢の大切さ
セミナーの最後に紹介されたのが「聴」という漢字でした。「聞く」と「聴く」は似ているようで意味が異なります。「聞く」は耳に入れること、「聴く」は耳・目・心を総動員して相手に向き合うことです。これはまさにアクティブリスニングの精神そのものであり、異文化理解において欠かせない姿勢だと感じました。
クラスメイトたちも「聴」という漢字の成り立ちに興味を示していましたが、私自身も「聴く」ことをこれからの留学生活で意識したいと思います。多様性を理解するには、まず相手の声に耳を澄ませ、心で受け止めること。それこそが文化という見えない壁を乗り越えるための、最もシンプルで確実な方法なのかもしれません。
おわりに
正直に言ってこのセミナーで得たことはすぐに役立つ実務スキルにつながるわけではありません。会計のように数字で成果が見えるものでもなく、マーケティングのようにフレームワークで整理できるものでもありません。でも、異文化に直面して立ち止まり、自分が当たり前だと思ってきた前提を問い直すという経験は、必ずどこかで生きてくる気がします。
先生によると、「グローバリゼーション」と「多様性」は現代を象徴する言葉です。しかし同時に語られる異文化理解というのは進んでいるようで全然進んでおらず、むしろ文化という見えない壁によって誤解や摩擦を生むこともあります。
その壁を越えるには、まず自分の「普通」が普通ではないことを理解すること、そして相手の「普通」に耳を傾けることが重要。
新しいものの見方を得ることができました。
参考 先生のTED×Aixプレゼンテーション